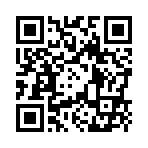「おはなし会」を開催しました(3/20)
桜が咲き始め、温かく感じる日も増えてきましたね。本日はおはなし会の直前に雨が降り始めるという悪天候の中でしたが、6組17名の御家族の方が足を運んでくださいました。
また、佐賀県立図書館ではインスタグラムを始めました。今回のおはなし会の様子も掲載される予定ですので、そちらもチェックしてみてください。
1.「世界でいちばんきれいな声」
本日は、すばなしからの始まりです。広い世界を見てみたい子ガモ。外の世界で様々な動物たちに出会います。みんな素敵な声の持ち主で、子ガモも同じように泣いてみたいと真似してみますが…。
おはなしのろうそく11巻より、子ガモの可愛らしい様子が目に浮かんでくるようなおはなしです。一緒に可愛い鳴きまねをしながら読んでみてください。

2.「ロージーのおさんぽ」
絵本の表紙が見えたところで「知ってる!」「読んだことある!」の声が聞こえてきました。昔からある本なので子どもさんだけではなく、お父さんやお母さんも一度は読んだことがあるかもしれません。
絵を見て楽しんでほしい一冊で、ページをめくるたびに皆さん熱心に絵本を見つめていました。
めんどりのロージーのお散歩風景が絵本一面に描かれていますが、一体どんな出来事が起きるのでしょうか。
絵が物語を語りかけてくるおはなしです。


3.「もういいかい」
色々なことが起こる、ハラハラするお散歩でしたね!次の絵本は二人の女の子のおはなしです。女の子は神社で何をして遊んでいるのかな?
「もういいかい?」「まあだだよ」の掛け声を使う遊びです。咲き誇る満開の桜、暖かな春の日のおはなしです。みなさんも絵本に出てきた女の子たちのように、これからの季節、桜を見ながら遊んでみてくださいね。


次回の「おはなし会」は、4月17日(土)15時からです。
今後の状況により、予定が変更になる場合があります。
佐賀県立図書館ホームページのお知らせを御確認ください。
また、佐賀県立図書館ではインスタグラムを始めました。今回のおはなし会の様子も掲載される予定ですので、そちらもチェックしてみてください。
1.「世界でいちばんきれいな声」
本日は、すばなしからの始まりです。広い世界を見てみたい子ガモ。外の世界で様々な動物たちに出会います。みんな素敵な声の持ち主で、子ガモも同じように泣いてみたいと真似してみますが…。
おはなしのろうそく11巻より、子ガモの可愛らしい様子が目に浮かんでくるようなおはなしです。一緒に可愛い鳴きまねをしながら読んでみてください。

2.「ロージーのおさんぽ」
絵本の表紙が見えたところで「知ってる!」「読んだことある!」の声が聞こえてきました。昔からある本なので子どもさんだけではなく、お父さんやお母さんも一度は読んだことがあるかもしれません。
絵を見て楽しんでほしい一冊で、ページをめくるたびに皆さん熱心に絵本を見つめていました。
めんどりのロージーのお散歩風景が絵本一面に描かれていますが、一体どんな出来事が起きるのでしょうか。
絵が物語を語りかけてくるおはなしです。


3.「もういいかい」
色々なことが起こる、ハラハラするお散歩でしたね!次の絵本は二人の女の子のおはなしです。女の子は神社で何をして遊んでいるのかな?
「もういいかい?」「まあだだよ」の掛け声を使う遊びです。咲き誇る満開の桜、暖かな春の日のおはなしです。みなさんも絵本に出てきた女の子たちのように、これからの季節、桜を見ながら遊んでみてくださいね。


次回の「おはなし会」は、4月17日(土)15時からです。
今後の状況により、予定が変更になる場合があります。
佐賀県立図書館ホームページのお知らせを御確認ください。
「おはなし会ピヨピヨ」を開催しました(3/17)
今日は、とても暖かくて、お花見日和の日ですね。
公園には、ピンク色の桜がとてもきれいに咲いています。
いつも通り、予約していただいた親子さんが3組参加してくださいました。
御参加いただいた御家族(大人3名、子ども3名)に検温をお願いして、密にならないように距離を取って座っていただきました。
司書からのいつもの3つのお願い(本を触った前と後は手を洗う・お友達とは離れて座る・マスクをつける)のお話の後に
さあ、「おはなし会ピヨピヨ」の始まりです。
1.「パンダ!」
『パンダ、パンダ』の言葉の後に『とんだ!』『〇〇だ!』『〇〇だ!』と言葉遊びが楽しい絵本です。色々なパンダさ んがいますよ。何をしているかな。

2.「いちご」
さあ、次はみんなが大好きないちごのお話ですよ。
どうやってあんなに美味しい実になるのでしょう。
あれ、あれそうなんだ~!
なるほど、そうやっていちごが美味しくなるんだね。
みんなで一緒にお口を開けて「あ~ん!」 もぐもぐ!
甘いかな~?それともすっぱいかな~?
お家でもいっぱい食べてみてね。

3.「だるまさんが」(大型絵本)
赤くて丸くて大きく膨らんでいるのはだあれだ?
「だ・る・ま・さ・ん・が~」どうしたのかな?
とっても気になるだるまさん! 伸びたり膨らんだり~!
ページをめくるととっても楽しい。
みんなもじーっと見てくれていました。

4.わらべうた「だるまさん」
お母さんにあぐらをかいてもらって、その間にみんなが入ってゆーらゆら。
だるまさんみたいにあっちむいてもコーロコロ!
こっちをむいてもコーロコロ!
いつでもいつでもコーロコロ!
ゆらゆらとお母さんの運動にも子どもさんの運動にもなりますよ。
スキンシップにもいいですよ。
お友達も嬉しそうにきゃっきゃっと笑いながら揺れていました。

次回の「おはなし会ピヨピヨ」は4月21日(水曜日)11時からの予定です。
参加希望の方は、児童室カウンターまたはお電話(0952-24-2900)にて事前予約をお願いします。
また、今後の状況により予定が変更になる場合がありますので、
佐賀県立図書館ホームページのお知らせを御確認ください。

公園には、ピンク色の桜がとてもきれいに咲いています。
いつも通り、予約していただいた親子さんが3組参加してくださいました。
御参加いただいた御家族(大人3名、子ども3名)に検温をお願いして、密にならないように距離を取って座っていただきました。
司書からのいつもの3つのお願い(本を触った前と後は手を洗う・お友達とは離れて座る・マスクをつける)のお話の後に
さあ、「おはなし会ピヨピヨ」の始まりです。
1.「パンダ!」
『パンダ、パンダ』の言葉の後に『とんだ!』『〇〇だ!』『〇〇だ!』と言葉遊びが楽しい絵本です。色々なパンダさ んがいますよ。何をしているかな。

2.「いちご」
さあ、次はみんなが大好きないちごのお話ですよ。
どうやってあんなに美味しい実になるのでしょう。
あれ、あれそうなんだ~!
なるほど、そうやっていちごが美味しくなるんだね。
みんなで一緒にお口を開けて「あ~ん!」 もぐもぐ!
甘いかな~?それともすっぱいかな~?
お家でもいっぱい食べてみてね。

3.「だるまさんが」(大型絵本)
赤くて丸くて大きく膨らんでいるのはだあれだ?
「だ・る・ま・さ・ん・が~」どうしたのかな?
とっても気になるだるまさん! 伸びたり膨らんだり~!
ページをめくるととっても楽しい。
みんなもじーっと見てくれていました。

4.わらべうた「だるまさん」
お母さんにあぐらをかいてもらって、その間にみんなが入ってゆーらゆら。
だるまさんみたいにあっちむいてもコーロコロ!
こっちをむいてもコーロコロ!
いつでもいつでもコーロコロ!
ゆらゆらとお母さんの運動にも子どもさんの運動にもなりますよ。
スキンシップにもいいですよ。
お友達も嬉しそうにきゃっきゃっと笑いながら揺れていました。

次回の「おはなし会ピヨピヨ」は4月21日(水曜日)11時からの予定です。
参加希望の方は、児童室カウンターまたはお電話(0952-24-2900)にて事前予約をお願いします。
また、今後の状況により予定が変更になる場合がありますので、
佐賀県立図書館ホームページのお知らせを御確認ください。
ワークショップ「おもしろ皿を作ってみよう!」を開催しました(2/21)
図書館の展示ホール等で陶芸展(1/28~2/23)を開催していただいた陶芸家興梠宜伸(こうろき よしのぶ)さんをお招きして、世界で一つだけの“おもしろ皿”を作るワークショップを開催しました。
参加者の方は、皆さん、検温と手指の消毒をされ、汚れ防止のためのエプロンを着用していただきました。


まずは、お皿部分の作成です。
型打ち成形という技法を使い、最初にお皿の形を作っていきます。ここが一番大切な作業になります。
型打ち成形は大量生産する際などによく使われる技法で、石膏などで作られた型に粘土を手のひらで打ち付けて、お皿を成形していきます。
机の上にあらかじめ準備された手回しろくろの中央に石膏で作ったお皿の型を置き、その上から厚みのある粘土を重ね、ろくろを回しながら手のひらの固い部分で粘土を打ち付け、中央部分から薄く延ばしていき、お皿を成形していきます。


握りしめた手で叩いたり指で力を込めたりすると、一部の生地のみ薄くなってしまうので注意!ゆっくりと均等に薄く延ばすことを意識してくださいと興梠さんからアドバイスがありました。
粘土を打ち付け、生地を延ばしていくと、型から徐々に粘土がはみ出してくるので、そのはみ出た部分を「切り弓」という道具で型の斜めになっている部分に合わせて切断していきます。
その作業を適度な薄さまで2~3回繰り返して粘土を延ばし、厚さを調整していきます。
ある程度生地が延び、形ができたら、さらしという布をかけ、粘土を叩きつけた際にできた生地のぼこぼこした部分を平らに滑らかにする作業を行います。
次に高台部分の作成です。
高台は基本的に何を作成しても大丈夫!世界に一つだけの個性に溢れたおもしろい高台を作ってください!という興梠さんからのお話があり、参加者の皆さんは、それぞれ自由に、高台の作成に取り掛かっていました。
手が支えているように見える高台や、人間が支えている姿、亀や恐竜、ひまわり、いちごの高台など、皆さん豊富な
アイデアで素敵なお皿を完成させていました。






出来上がったお皿はまずじっくりと乾燥させ、780度くらいの温度で素焼きをし、釉薬を塗った後、1250度くらいの温度で本焼きをします。
お皿は興梠さんが有田に持ち帰り、焼いてきてくださるので、本日参加された皆さんにはお皿の引換券を渡し、焼きあがったら図書館まで取りに来ていただきます。
お皿がどんな風に焼きあがるのか、皆さんワクワクしている様子でした。
本日のワークショップは、午前の部と午後の部大人1名、子ども7名、合計8名ずつの参加でした。
今後も、図書館では、様々な行事を行う予定ですので、ご期待ください。
参加者の方は、皆さん、検温と手指の消毒をされ、汚れ防止のためのエプロンを着用していただきました。


まずは、お皿部分の作成です。
型打ち成形という技法を使い、最初にお皿の形を作っていきます。ここが一番大切な作業になります。
型打ち成形は大量生産する際などによく使われる技法で、石膏などで作られた型に粘土を手のひらで打ち付けて、お皿を成形していきます。
机の上にあらかじめ準備された手回しろくろの中央に石膏で作ったお皿の型を置き、その上から厚みのある粘土を重ね、ろくろを回しながら手のひらの固い部分で粘土を打ち付け、中央部分から薄く延ばしていき、お皿を成形していきます。


握りしめた手で叩いたり指で力を込めたりすると、一部の生地のみ薄くなってしまうので注意!ゆっくりと均等に薄く延ばすことを意識してくださいと興梠さんからアドバイスがありました。
粘土を打ち付け、生地を延ばしていくと、型から徐々に粘土がはみ出してくるので、そのはみ出た部分を「切り弓」という道具で型の斜めになっている部分に合わせて切断していきます。
その作業を適度な薄さまで2~3回繰り返して粘土を延ばし、厚さを調整していきます。
ある程度生地が延び、形ができたら、さらしという布をかけ、粘土を叩きつけた際にできた生地のぼこぼこした部分を平らに滑らかにする作業を行います。
次に高台部分の作成です。
高台は基本的に何を作成しても大丈夫!世界に一つだけの個性に溢れたおもしろい高台を作ってください!という興梠さんからのお話があり、参加者の皆さんは、それぞれ自由に、高台の作成に取り掛かっていました。
手が支えているように見える高台や、人間が支えている姿、亀や恐竜、ひまわり、いちごの高台など、皆さん豊富な
アイデアで素敵なお皿を完成させていました。






出来上がったお皿はまずじっくりと乾燥させ、780度くらいの温度で素焼きをし、釉薬を塗った後、1250度くらいの温度で本焼きをします。
お皿は興梠さんが有田に持ち帰り、焼いてきてくださるので、本日参加された皆さんにはお皿の引換券を渡し、焼きあがったら図書館まで取りに来ていただきます。
お皿がどんな風に焼きあがるのか、皆さんワクワクしている様子でした。
本日のワークショップは、午前の部と午後の部大人1名、子ども7名、合計8名ずつの参加でした。
今後も、図書館では、様々な行事を行う予定ですので、ご期待ください。
「おはなし会」を開催しました(2/20)
一昨日は、雪がチラチラ降り、凍えるような寒さでしたが、「こころざしの森」広場では、カンザクラが咲き始め、暖かな日になりました。
今日は12組のご家族の方に(大人の方12名、子どもさん22名)ご参加いただきました。
いつものように、司書から皆さんへ新型コロナ感染予防対策の3つのお願い(本を触った後は手を洗う・お友達と離れて座る・マスクをつける)をして「おはなし会」の始まりです。

最初の「おはなし」はもっと温かくなるおはなしからです。
1.「もりのおふろ」
森の奥でおふろが湧いています。ライオンさんがやってきて、ぞうさんがやってきて…。動物たちが次々にやってきて。何がはじまるでしょう?
とっても仲良しの動物たちのおはなしです。


2.すばなし「だめといわれてひっこむな」
絵本がなく、想像しながらきいてもらう「すばなし」を司書がおはなししました。
おばあさんと子ネズミの心温まるやり取りに子ども達はじっと静かに聞いてくれました。


3.「ぽとんぽとんはなんのおと」
森の穴の中でクマのお母さんはふたごの坊やを産みました。外からさまざまな音が聞こえてきます。どんな春の音が聞こえてくるでしょう?

今日は12組のご家族の方に(大人の方12名、子どもさん22名)ご参加いただきました。
いつものように、司書から皆さんへ新型コロナ感染予防対策の3つのお願い(本を触った後は手を洗う・お友達と離れて座る・マスクをつける)をして「おはなし会」の始まりです。

最初の「おはなし」はもっと温かくなるおはなしからです。
1.「もりのおふろ」
森の奥でおふろが湧いています。ライオンさんがやってきて、ぞうさんがやってきて…。動物たちが次々にやってきて。何がはじまるでしょう?
とっても仲良しの動物たちのおはなしです。


2.すばなし「だめといわれてひっこむな」
絵本がなく、想像しながらきいてもらう「すばなし」を司書がおはなししました。
おばあさんと子ネズミの心温まるやり取りに子ども達はじっと静かに聞いてくれました。


3.「ぽとんぽとんはなんのおと」
森の穴の中でクマのお母さんはふたごの坊やを産みました。外からさまざまな音が聞こえてきます。どんな春の音が聞こえてくるでしょう?

おはなし会ピヨピヨを開催しました(2/17)
昨日まで暖かい日が続いていましたが、今日は朝から雪が降り、冷え込みました。
そんな中4組のご家族が参加してくださいました。

「おはなし会ピヨピヨ」は、月に一度の開催とし、事前に参加の予約をしていただき、当日参加される方の検温をお願いしております。また、手指の消毒や、隣同士の距離を取っていただくなど、新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力していただいています。
1.「あかちゃんたいそう」
いろんな動物や、生き物が出てくるお話です。
あかちゃんがいろんな動物や生き物と体操をします。
ねこちゃん 、ぞうさん、いぬさん
、ぞうさん、いぬさん …。最後は誰とどんな体操をするでしょう?
…。最後は誰とどんな体操をするでしょう?
寒い日は体を動かしてポカポカになりましょうね。

2.「ねられんねられんかぼちゃのこ」
夜になってもかぼちゃの子はなかなか眠れません。どうしたらゆっくり眠れるでしょうか。
お月さんとかぼちゃの子のやり取りが楽しい絵本です。


3.パネルシアター
たまごがコロンと転がってコロコロパチンと割れました。
司書がたまごから次々といろんなかわいい生き物を出してくれました。
パチンと割れて、中から何が出てきたかな?
子どもさんたちは静かにお話を聞いてくれました。


次回の「おはなし会ピヨピヨ」は3月17日(水曜日)11時からの予定です。
参加希望の方は、児童室カウンターまたは電話(0952-24-2900)にて事前予約をお願いします。
また、今後の状況により予定が変更になる場合があります。
佐賀県立図書館ホームページのお知らせをご確認ください。
そんな中4組のご家族が参加してくださいました。

「おはなし会ピヨピヨ」は、月に一度の開催とし、事前に参加の予約をしていただき、当日参加される方の検温をお願いしております。また、手指の消毒や、隣同士の距離を取っていただくなど、新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力していただいています。
1.「あかちゃんたいそう」
いろんな動物や、生き物が出てくるお話です。
あかちゃんがいろんな動物や生き物と体操をします。
ねこちゃん
 、ぞうさん、いぬさん
、ぞうさん、いぬさん …。最後は誰とどんな体操をするでしょう?
…。最後は誰とどんな体操をするでしょう?寒い日は体を動かしてポカポカになりましょうね。

2.「ねられんねられんかぼちゃのこ」
夜になってもかぼちゃの子はなかなか眠れません。どうしたらゆっくり眠れるでしょうか。
お月さんとかぼちゃの子のやり取りが楽しい絵本です。


3.パネルシアター
たまごがコロンと転がってコロコロパチンと割れました。
司書がたまごから次々といろんなかわいい生き物を出してくれました。
パチンと割れて、中から何が出てきたかな?
子どもさんたちは静かにお話を聞いてくれました。


次回の「おはなし会ピヨピヨ」は3月17日(水曜日)11時からの予定です。
参加希望の方は、児童室カウンターまたは電話(0952-24-2900)にて事前予約をお願いします。
また、今後の状況により予定が変更になる場合があります。
佐賀県立図書館ホームページのお知らせをご確認ください。
ワークショップ「古文書を使ってトートバッグを作ろう」
今日は佐賀県立図書館に保存されている古文書「龍造寺家古文書」から見つかった花押(かおう)を使って自分のトートバッグに押印して作成してみようというワークショップの紹介です。
郷土調査担当主催で2月7日(日曜日)に「こころざしの森」で開催されました。

新型コロナウイルス対策のためにアルコール消毒と検温をお願いして、各自の席へ座っていただきました。
午前の部は11名の方が参加してくださいました。
まずはプロジェクターで勉強しましょう。

今日、使っていただく「花押」(かおう)というのはいったい何でしょうか?
それは、昔の武将が、自分が出した手紙に印(しるし)として自分でデザインしたものを自分の証(あかし)として用いたもので、今でいう印鑑のようなものですね。
この古文書からは徳川家康・足利義明・足利尊氏・龍造寺隆信の花押が見つかっています。とてもすごいことですよね。
サインであるがゆえにオリジナル性がとても大事とされています。
古文書を見る機会があれば他の花押を探してみてくださいね。
佐賀県立図書館のデータべースからも探せますので是非活用してください。

このような説明を聞いてトートバッグの作成を開始しました。
なかなか下書きが決まりません。どんなバッグにしましょうか?
さあ、色々な花押を押しましょう。
赤、青、緑、黒、ピンクの五色の中から何色を使おうかな?
どの場所に押そうかな?

小さい子どもさんにはステンシルが大人気でした。
大きな〇や小さな△、□。枠をこすって塗りますよ。

花押を使ってミッキーさんの顔を作る方もいらっしゃいました。
最初は押すのもこわごわー。でも、だんだんと慣れてきて手の動かし方も早い、早い。

なるほど、トートバッグの中に新聞紙を入れるとクッションになってくっつきません。
いっぱい押したらスタッフの方にドライヤーで乾かしてもらいます。
やっと、自分だけのトートバッグができました。


参加してくれたお友達は図書館に行く時にこのバッグを持っていきたいと話してくれました。
本当に楽しく喜んでもらえてよかったですね。
午後の部も11名の方が参加してくださって、楽しく終了しました。
郷土調査担当主催で2月7日(日曜日)に「こころざしの森」で開催されました。

新型コロナウイルス対策のためにアルコール消毒と検温をお願いして、各自の席へ座っていただきました。
午前の部は11名の方が参加してくださいました。
まずはプロジェクターで勉強しましょう。

今日、使っていただく「花押」(かおう)というのはいったい何でしょうか?
それは、昔の武将が、自分が出した手紙に印(しるし)として自分でデザインしたものを自分の証(あかし)として用いたもので、今でいう印鑑のようなものですね。
この古文書からは徳川家康・足利義明・足利尊氏・龍造寺隆信の花押が見つかっています。とてもすごいことですよね。
サインであるがゆえにオリジナル性がとても大事とされています。
古文書を見る機会があれば他の花押を探してみてくださいね。
佐賀県立図書館のデータべースからも探せますので是非活用してください。

このような説明を聞いてトートバッグの作成を開始しました。
なかなか下書きが決まりません。どんなバッグにしましょうか?
さあ、色々な花押を押しましょう。
赤、青、緑、黒、ピンクの五色の中から何色を使おうかな?
どの場所に押そうかな?

小さい子どもさんにはステンシルが大人気でした。
大きな〇や小さな△、□。枠をこすって塗りますよ。

花押を使ってミッキーさんの顔を作る方もいらっしゃいました。
最初は押すのもこわごわー。でも、だんだんと慣れてきて手の動かし方も早い、早い。

なるほど、トートバッグの中に新聞紙を入れるとクッションになってくっつきません。
いっぱい押したらスタッフの方にドライヤーで乾かしてもらいます。
やっと、自分だけのトートバッグができました。


参加してくれたお友達は図書館に行く時にこのバッグを持っていきたいと話してくれました。
本当に楽しく喜んでもらえてよかったですね。
午後の部も11名の方が参加してくださって、楽しく終了しました。